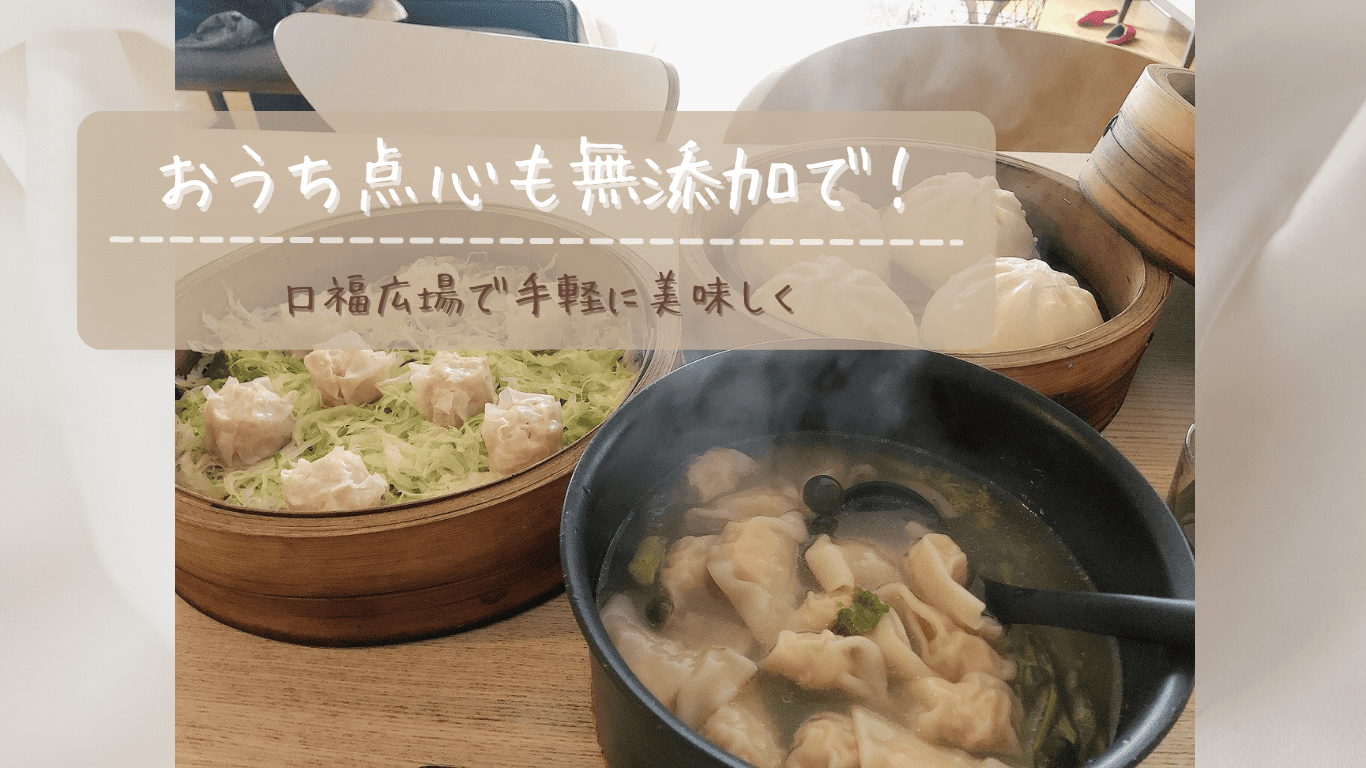「無添加生活」は選択であって義務じゃない
「子どものために」「自分の健康のために」と、無添加を意識した食生活を始めた方は多いのではないでしょうか。
けれど、完璧を目指そうとすればするほど、ストレスや罪悪感がつきまといがちです。
私自身、かつては無添加、マクロビ、ヴィーガン、ローフードなど、さまざまな食生活に挑戦してきました。
一つのやり方に傾倒すると、いつのまにか視野が狭くなってしまう——そんな“怖さ”も感じてきた経験があります。
だからこそ今は、「完璧じゃなくていい」と、自分に許可を出すようにしています。
“今日の選択が私と家族にとって心地よいか”を軸に、柔軟な無添加との付き合い方を目指しています。
どこで「ほどほど」を決める?自分ルールの作り方
無添加生活を続けるうえで、最初に考えたいのが「どこまでを無添加にするか?」という基準づくりです。
例えば、次のような自分ルールがおすすめです。
- 子どもが体調を崩しやすいときは、添加物少なめの食事を意識
- 外食やお呼ばれの日は割り切って楽しむ
- 加工品を選ぶときは「無添加寄り」を意識
- お菓子は週末だけ“ちょっといい素材のもの”に
無理をせず、生活や家族の状況に合わせて「ゆるく決める」。
それが続けやすさにつながります。
生活に取り入れる「ゆる無添加」の基本ステップ
「無添加、難しそう…」と思うかもしれませんが、まずは日常に取り入れやすいところから始めましょう。
たとえば…
- 調味料を“無添加”のものに変えてみる(味噌、しょうゆ、だしなど)
- スーパーでは加工品より素材中心で選ぶ
- 忙しい日は無理せず市販品を活用する
- おやつは「ドライフルーツ+ナッツ」など、準備が楽で満足感のあるものに
特に印象的だったのが、真夏の空手大会で子どもに持たせた添加物入りのシャーベットゼリー。
暑さ対策として「今、必要なこと」に目を向けて選んだ結果でした。
“その時の目的に適っていればOK”という判断は、健康意識と現実のバランスをとるうえで大切な視点です。
無添加生活を続けるコツと折り合いのつけ方
“がんばりすぎないこと”が、長く続けるためのコツです。
「今日は無理だから○○を使っちゃおう」「忙しい週は冷凍食品で助かろう」
そんな風に自分にやさしくできると、罪悪感に悩まずにすみます。
そしてもうひとつ大事なのが、「五感を大切にすること」。
・なんとなく美味しく感じる
・安心できる香りがする
・疲れているときに、温かいスープでほっとする
この“感じる力”をベースに選んでいくと、無添加生活はもっと楽しいものになります。
具体例で見る「ほどほど無添加」の実践例
わが家で意識している“ほどほど無添加”のスタイルを一部ご紹介します。
| シーン | 無添加できる範囲 | 妥協ポイント |
|---|---|---|
| 平日の夕飯 | 素材+調味料の簡単手作り | 習い事や急な用事などで手作りが厳しい時は総菜・外食あり |
| 外出・イベント | おにぎりやフルーツを持参 | 市販ジュースやお菓子もあり |
| おやつ | 焼きいも、手作りプリンや杏仁豆腐、手作りパン | 外出先で食べる市販おやつOK |
| 忙しい日の夜 | 無添加レトルトや無添加冷凍食材で調整 | 外食で済ませるのも選択肢のひとつ |
「どこを手作りして、どこで手を抜くか」のメリハリを持つと、心にも時間にも余裕が生まれます。
値段や手間を気にせず、無添加を賢く取り入れるヒント
無添加の食品は価格が高いイメージがあるかもしれません。
でも、手間やコストを抑えながら取り入れる工夫もあります。
- 調味料は“少し良いもの”を買い、食材はシンプルに
- 無添加でもコスパのよいメーカーを見つけてリピート
- ネット通販や自然食品店のまとめ買いで節約
- 「作ったほうが高い・手間がかかる」ときは市販品に頼る
価格や手間と相談しながら“無理せず続ける”ことが、長い目で見ると結果的に賢い選択になると感じます。
“無添加”より大切な視点って?総合的な食選択の考え方
ここまで書いてきましたが、実は私自身「添加物=悪」とは思っていません。
それよりも、
- 食べる量や頻度
- 食材のバリエーション
- 調理法や食べるタイミング
…など、食の“全体バランス”のほうが体感的に影響が大きいと感じています。
子どもとの暮らしでは、「イベント=楽しい」「みんなと一緒=うれしい」という気持ちのほうが、体にとってもよい影響があると思うこともあります。
長く続く「ほどほど無添加」生活のための心構え
無添加を取り入れることで、“自分と家族を大切にする時間”が生まれます。
でも、それが「~しなければ」「~してはいけない」に変わったとき、心はどんどん苦しくなります。
- 小さな一歩から始めよう
- 自分にやさしく、家族にやさしく
- 失敗も経験と受けとめよう
- 今日は今日、また明日から
そんな風に、自分と折り合いをつけながら、五感がよろこぶ暮らしをこれからも続けていきたいと思います。