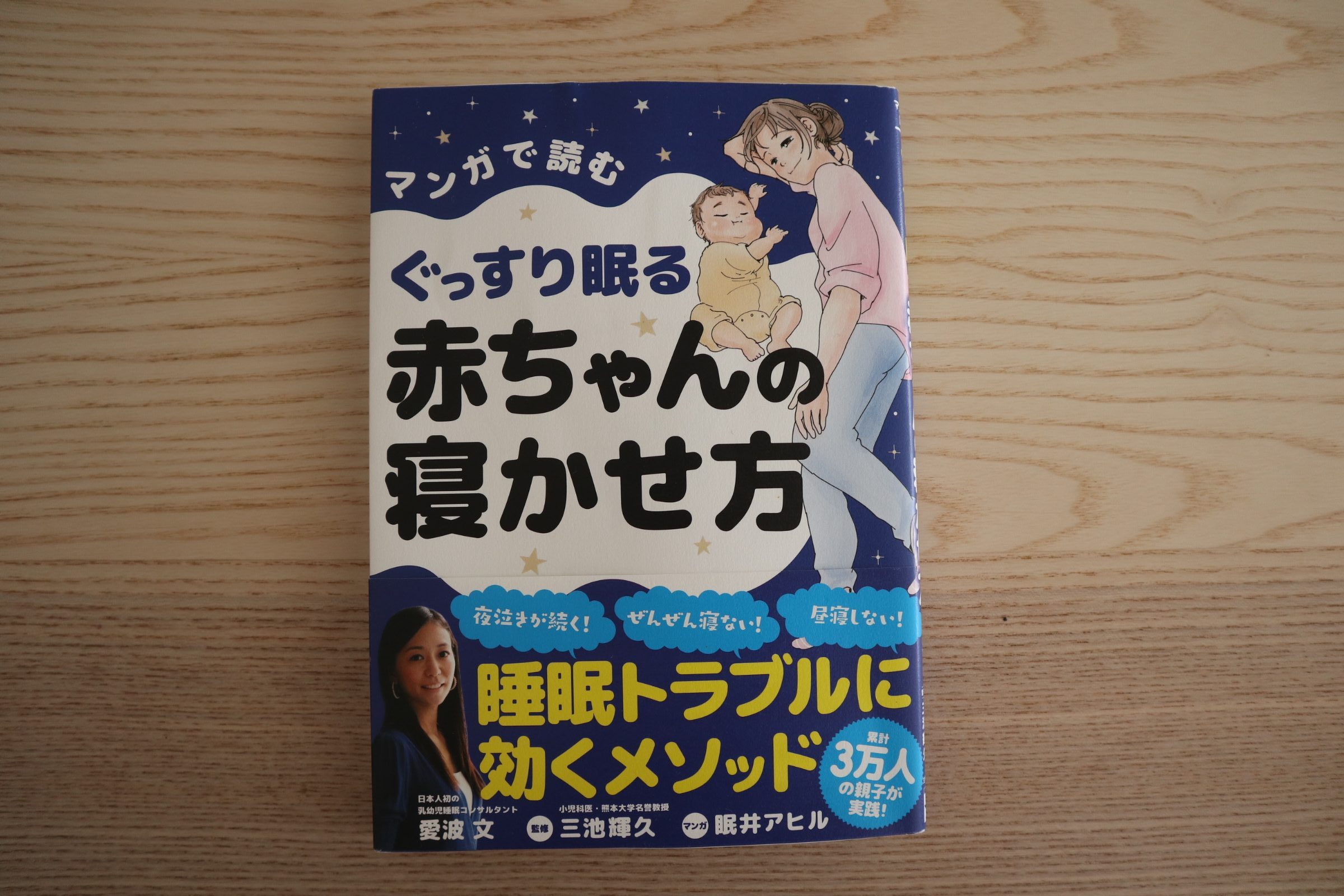瞑想の効果と、わたしが続けたくなる理由
「心を整える」って、こういうことかもしれない
子育て、仕事、家のこと。
一日が終わるころには、頭の中がぐるぐるしている。
「ぼーっとしたいのに、考えごとが止まらない」——そんな夜に出会ったのが、瞑想でした。
ヨガのクラスで何度か体験していたけれど、当時は「呼吸に意識を向ける時間」くらいの感覚。
でも、最近は“瞑想の科学的な効果”が次々と明らかになっていて、改めて「これはすごい」と感じています。
今回は、研究で確認されている瞑想の効果と、私自身の実践から感じたことをまとめてみました。
瞑想で得られる5つの効果
① うつ・ストレスに効果がある
瞑想を行うと、脳内の「前頭前皮質」や「扁桃体」など、情動に関わる部位の働きが活発になることがわかっています。
長期間の継続によって、これらの部位の“厚みが増す”という報告も。
アメリカでは大企業の研修にも取り入れられ、「マインドフルネス」という言葉が一般化しました。
ストレスで呼吸が浅くなっているときこそ、5分だけでも“呼吸に意識を向ける”時間を持つと、頭の中のノイズが少しずつ静まっていく感覚があります。
② 神経質・不安傾向をやわらげる
心理学では、性格を5つの要素に分ける「ビッグ・ファイブ理論」があります。
その中のひとつ、「神経症的傾向(ネガティブ感情の感じやすさ)」が高い人ほど、ストレスや不安を感じやすいと言われます。
瞑想には、この“神経症的傾向”を和らげる効果があることが示されています。
不安に飲み込まれそうなときも、呼吸に意識を戻すだけで「今ここ」に立ち返ることができる——そんな小さな安定をくれるのが瞑想です。
③ ダイエットにもプラス
意外ですが、瞑想は「感情のコントロール力」を高めるため、食べすぎ防止にもつながります。
マインドフルネス状態では前頭葉が活性化し、衝動的な行動よりも「理性的な選択」がしやすくなるのです。
たとえば「ストレスでつい甘いものに手が出る」も、瞑想を続けるうちに少しずつ減っていく感覚があります。
④ 集中力が上がる
これは、すぐに実感できる効果。
研究によると、わずか10分の瞑想でも集中力が高まるそうです。
プレゼンや仕事の前、家事や勉強に取りかかる前に、静かに呼吸を整えるだけで、頭がクリアになります。
⑤ マルチタスクの害から守ってくれる
「資料を作りながらチャット対応」「子どもの話を聞きながら夕飯準備」——
現代人は常に“ながら”状態。でも、これは脳にとってストレスです。
マルチタスクが続くと、集中力の低下や不安感、ミスの増加を招くといわれています。
瞑想には、そんな“分散した注意”をリセットする効果があります。
継続的に行うことで、記憶力や認知機能を保つという実験結果も報告されています。
私の瞑想とのつきあい方
ヨガインストラクターをしていた頃は、クラスの終わりに5〜10分ほど呼吸瞑想をしていました。
赤ちゃんとの生活が中心になってからは、計画的に時間を確保するのが難しい日々ですが、
「授乳後に3分だけ」「寝かしつけのあとに5分だけ」と、短い時間でも“やる”を優先するようにしています。
DaiGoさんのD-Labで科学的な知見を知ってからは、瞑想が「感覚的なもの」ではなく、ちゃんと脳科学で裏づけられていると理解できて、習慣化のモチベーションが上がりました。
習慣化の目安:8週間続けてみよう
多くの研究では、瞑想の効果を得るには8週間程度の継続が推奨されています。
1日10分、週に数回でもOK。
お金もかからず、副作用もない——これほど“コスパのいい”メンタルケア、なかなかありません。
まとめ:完璧を目指さなくていい
瞑想って「静かに座って心を無にする」みたいなイメージがありますが、
実際は「雑念が出てもOK」「途中で寝てもOK」。
呼吸を意識して“今ここ”に戻る、その繰り返しです。
私も毎日きっちりはできません。
でも、5分でもやると体と心の余白が生まれる感覚があって、やっぱりいいなと思う。
——瞑想は、“がんばりすぎた自分”を休ませる小さなリセットボタン。
そんなふうに思っています。
参考文献・出典
- Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living.
- Davidson, R.J. et al. (2003). Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation.
- DaiGo「Dラボ」配信より