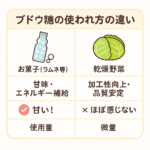BPA(ビスフェノールA)とは?危険性が注目される理由
BPA(ビスフェノールA)は、プラスチックや缶詰の内側コーティングなどに使われてきた化学物質です。特に食品用の缶詰では、金属の腐食や中身の酸化を防ぐために、BPAを含むエポキシ樹脂が使われているケースがあります。
私たちが日常的に手に取るトマト缶や鯖缶、ペットボトル、紙コップの内側など、さまざまな製品に使われており、意識しないうちにBPAに触れていることが少なくありません。
BPAの健康リスク|妊娠中や子どもへの影響は?
BPAは「内分泌かく乱物質」として知られています。つまり、体内のホルモンと似た作用を持ち、ホルモンバランスを乱す恐れがあります。特に以下のリスクが指摘されています。
- 女性ホルモン様作用による生殖機能への影響
- 小児の神経発達(注意欠陥や自閉スペクトラム症など)への影響
- 代謝異常や肥満、糖尿病のリスク上昇
- 前立腺がん・乳がんなどとの関連
動物実験によるデータが多く、人間に対する直接的な影響は「量やタイミングによる」とされていますが、胎児や小さな子どもに対する曝露はとくに注意が必要です。
缶詰に含まれるBPA量は?トマト缶・鯖缶の実態
酸性の強い食品(トマトなど)は、BPAが缶の内側から溶け出しやすい傾向があります。
一部の研究による実測値(目安)
| 食品 | BPA検出濃度(目安) |
|---|---|
| トマト缶 | 約0.1〜0.14mg/kg |
| 鯖缶・ツナ缶 | 0.01〜0.05mg/kg程度 |
欧州食品安全機関(EFSA)は2023年に一日耐容摂取量(TDI)をこれまでの2万分の1まで引き下げ、2024年にはEU圏で食品包装へのBPA使用を原則禁止としています。
日本国内では規制は緩やかですが、企業によっては自主的にBPAフリーの包装材に切り替える動きも見られます。
BPAの摂取量と健康リスク|日常生活での影響は?
現在のところ、通常の食生活の範囲で摂取するBPAは「多くの人にとって基準値以下」と評価されています。
ただし、缶詰を日常的に多用している家庭では、体内のBPA濃度が上昇する可能性があるという報告もあり、以下のような人は特に注意が必要です。
- 妊娠中や授乳中の方
- 幼児や乳児のいるご家庭
- 缶詰を週に何度も使用する方
「基準以下だから安心」と捉えるか、少しずつでもBPAの摂取を減らす生活を心がけようと考えるか、少々意見が割れるところかもしれませんが、未知の(将来の)健康リスク低減を少しでも減らしたい方は次で紹介する代替品を検討してみてください。
BPAフリー缶詰の見分け方と安全な代替食品
BPAを100%避けるのは難しいですが、「選び方」を知っておくことで摂取量を減らすことはできます。
BPA対策のポイント
- BPAフリー表示がある製品を選ぶ
⇒ 海外製のオーガニック食品や一部国産品で確認可能 - ガラス瓶・レトルトパウチ・冷凍食品などを代替品に
⇒ トマトソースやツナは、パウチや瓶詰で販売されているものも - 缶詰は器に移してから加熱
⇒ 缶のまま加熱するとBPAの溶出リスクが高まる可能性があります - 使用頻度を見直す
⇒ 週に何度も使用していないか振り返りを - メーカーに問い合わせる
⇒ BPAフリーをうたっていなくても、すでに代替樹脂に切り替えている場合もあります
【まとめ】トマト缶・鯖缶を選ぶときに気をつけたいこと
缶詰は忙しい日々の味方。すべてを避ける必要はありませんが、家族の健康を考えるなら「知って選ぶ」姿勢が大切です。
実践しやすいまとめリスト
- 「毎日」ではなく「週に1〜2回」に
- 酸性食品(トマト系)は瓶詰などの代替も活用
- 「BPAフリー」表記を探してみる
- 温める前に別容器へ移す
- 妊娠中・乳幼児期は意識して選ぶ
過剰な不安にとらわれず、ちょっとした工夫で「軽やかに」BPAとの付き合い方を見直していけるといいですね。
参考文献・信頼できる情報リンク
- Health effects of Bisphenol A – Wikipedia
- Bisphenol A in canned foods: A systematic review – Wiley Online Library
- Nutrients: Effect of Canned Foods Consumption on Urinary BPA
- Nature: BPA in Iranian canned foods (2024)
- EFSA Opinion on BPA (2023)